はじめに
突然ですが、皆さんは収入源を複線化できていますか?
(平たく言うと、色々なところからの収入源がありますか?)
複線化というと難しく感じますが、要は勤務先といった1か所からのお給料しか、大きな収入源ないかどうか、ということです。

お給料以外に、
・銀行預金の利息
・株式投資による配当金収入
・不動産投資による家賃収入
・国・自治体からの手当
・副業による収入
等が、挙げられますね。
最初に結論を述べると、収入源を複線化させておくことで、一つの収入源の調子が良くなかったとしても、他の収入源が存在することによる精神的な安定が得られます。
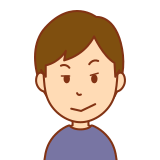
それなら大丈夫。。
株式投資とか不動産投資をしてなくても、
給料と銀行預金の利子があるから、
収入源は複線化されているので。

たしかに、給料+銀行利息で複線化はされていますが、
銀行利息はどれくらい振り込まれていますか?
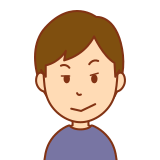
半年に1回、
数十円~数百円。。

お給料以外の複線化の対象が、
銀行利息だけだと、心もとないですね。
複線化するだけでなく、
1つ1つの収入源の規模にも着目したいところです。
筆者の場合、毎年12月は一年を通じて最も入金額が多いため、より一層収入源の複線化の意義を感じます。金額的な意味合い以上に、精神的な意味も大きいです。
本記事では、収入源を複線化することの大切さについてまとめます。
所感 ※収入源を複線化することの大切さ
本件の所感は以下です。
- 収入源の複線化とは具体的には?
- 収入源を複線化することの効用(メリット)は?
- 収入源を複線化したことを実感するために必要なことは?
- ご参考:収入の複線化(筆者の事例)

一つずつ見ていきます。
収入源の複線化とは具体的には?
収入源の複線化するいには、色々な所得を増やすことが考えられます。
所得税法上の所得の区分としては以下の10種類があります。
- 利子所得★ →預貯金や債券の利子等
- 配当所得★ →株式の配当金等
- 不動産所得 →不動産等の貸付による賃料等
- 事業所得★ →事業から生じた所得
- 給与所得★ →会社員の給与、賞与等
- 退職所得 →退職金等
- 山林所得 →山林伐採の譲渡による所得等
- 譲渡所得 →資産の売却等で得た所得
- 一時所得 →生命保険の満期保険金等
- 雑所得 →公的年金等や業務(副業)、その他の収入
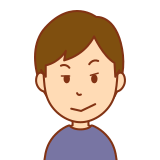
10種類。。
覚えられない。。

安心してください。
上記★を付けている4つの所得が今回の記事のメインなので、
まずは、その4つの所得を把握してもらえれば大丈夫です。
上記の所得に分類されないものもありますが、収入源の主体ごとに分類すると、以下になります。
- 会社 →給与・賞与(給与所得)
- 銀行 →利息(利子所得)
- 証券会社 →株式配当金、株式譲渡所得(配当所得・譲渡所得)
- 国 →児童手当
- 自治体 →各種自治体からの手当
- 税務署 →所得税還付(住宅ローン控除を利用している場合等)
- 副業 →副業収入(事業所得 or 雑所得)
上記のように、所得だけでなく、各種手当や税還付も含めて、最終的に自身の銀行口座もしくは証券口座に蓄えられる収入源が数多く考えられます。
サラリーマンをしていると、ついつい会社からの給料しか大きな収入源が無いと思いがちですが、会社からお給料以外にも収入源を増やすかは、終身雇用制が崩壊しつつある現代で非常に大切なことだと感じます。

1つの会社に勤めあげる代わりに、
年功序列かつ終身雇用制で給与が右肩上がり、
という社会情勢は終わりを迎えていますね。
収入源を複線化することの効用(メリット)は?
収入源を複線化するメリットは、ずばり以下だと考えます。
・会社の給与・賞与と、銀行の微々たる利息だけが、資産形成でない、という余裕が生まれる。

つまり、
”心の余裕 = 精神的な豊かさにつながる”
ということですね。
会社からの給料しかないといった状況だと、以下のようなことになりかねません。
- 上司から無理難題を押し付けられても、Noと言えない。
- 会社の中での出世競争や評価に戦々恐々とする。
- ”生きるために会社で働く”はずが、”働くために生きている”という本末転倒な状況に。。
つまり、自分自身の生殺与奪権が自分ではなく会社にあると考えてしまいがちです。
しかし、自分の人生に全責任を負えるのは自分自身でしかありません。
会社は、自分の人生の中の一つの選択肢・手段でしかありません。
そういった意味で、会社以外からの収入源があると、精神的な余裕が違ってきます。

勤め先の会社で理不尽な要求をされても、
毅然と断ることもできるのではないでしょうか。
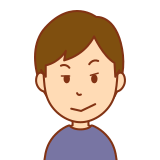
たしかに、
そりの合わない上司への対応にも
余裕が生まれそう。。
収入源を複線化したことを実感するために必要なことは?

これまた、ずばり以下だと考えます。
家計管理により、口座入金される金額の発生源をしっかりと区別・認識すること
給与・賞与、利子、手当等、色々なところから発生したものも、最終的には口座に数字として合算されます。つまり、口座入金されるとただの数字の羅列になってしまいます。
金額的な増加を実感するだけであれば、口座の累計金額を確認するだけで十分です。
しかし、ここで実感したいのは収入源の複線化。
つまり、色々なところからの収入が発生し、自身の口座を潤しているという実感です。
そのために、しっかりと家計簿へ収入の記帳をしっかりし金額を区別して管理できるようにしておくことが望ましいです。

筆者は、この収入の複線化を実感できるので、
家計簿をつけるのが楽しみで仕方がありません。
かれこれ、家計簿を毎日つけ続けること10年。
もはや、無意識の境地で、家計簿をつけています。
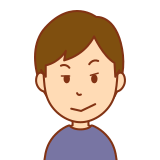
無意識の境地。。
良い意味で変態ですね。。

。。
筆者自身は、家計簿や管理がもともと苦でないです。
しかし、もしもそうした家計管理等が苦手な方で、家計管理が続かないという場合は、せめて銀行口座の通帳記帳は毎月しっかりして、口座入金される金額が色々なきっかけで発生していることを認識するだけでも、だいぶ違うと思います。

紙の通帳だと、足を運んでの記帳作業が億劫なので、
ネット銀行での、電子通帳等が良いかもしれません。
いずれにしても、せっかく収入の複線化ができていたとしても、それを実感する仕組みが整っていないのは、すごくもったいない事です。
家計管理なり通帳記入なり、ご自身のやり易い方法で、しっかりと認識していきましょう。

大前提として、
収入の複線化をしていきましょう。
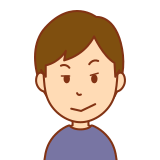
はい!!
ご参考:収入の複線化(筆者の事例)
余談ですが、筆者の場合、具体的には以下のような手段で収入の複線化を図っています。
- 会社 →給与・賞与(給与所得)
…会社員としてのお給料・ボーナスです。現在最も核となる安定収入です。ゆくゆくは、株式投資や副業による収入だけで生計が立てられるようになったら会社員卒業もあるかもしれません。いわゆるFIREですね。 - 銀行 →利息(利子所得)
…筆者の銀行預金の利息は数百円程度と微々たるものです。収入源の一つであることに変わりありませんが、これだけだと資産形成への貢献は薄いですね。投資や副業といった別の収入源との組み合わせが必要と感じます。 - 証券会社 →株式配当金、株式譲渡所得(配当所得・譲渡所得)
…収入の複線化として、会社員としての給与・賞与以外の大きな柱はここになります。
以下のような状況です。市場の相場観にもよりますが、株価上昇や円安が進んでいると資産が、8桁レベルで数年で増える爆発力を実感できます。
・投資信託 …旧つみたてNISA+新NISA。オルカンor全米株式インデックスファンド。
・米国株ETF …VOO。VT。
・個別株少々 …趣味程度のアップル株(AAPL) - 国 →児童手当等
…目下、2人(小1⁺年少)を育てている身としては、児童手当も大きな収入の一つです。毎年25万円 ~ 30万円程度の口座入金があるため、金額的に馬鹿にできません。出生時や転入・転出時に、役所にしっかり手続きしましょう。 - 自治体 →各種自治体からの手当
…東京都在住ということもあり、だいぶ手当が厚い印象があり、助かっています。最近だと、東京都018サポートで、18歳未満の子供1人6万円/年の支給があるため、2人で年12万円。これもまた、馬鹿にできない金額です。こうした、申請による手当もしっかり忘れずに申請・受給していきましょう。 - 税務署 →所得税還付(住宅ローン控除を利用している場合等)+節税
…持ち家のため住宅ローン控除も活用しています。また、ふるさと納税の寄付金控除、医療費控除といった、税優遇制度も積極的に活用しています。特に、ふるさと納税の寄付金控除と医療費控除は、会社員の年末調整では対応できず、確定申告が必要となりますが、こうしたお得な制度をかつようするためにも、確定申告は誰しもに必要な作業ということになります。e-Tax等電子申告でだいぶ作業負荷は減っているので、積極的に活用していきましょう。 - 副業 →副業収入(事業所得 or 雑所得)
…ここは、まだまだ挑戦中のところもあり、何とも言えませんが、アフィリエイトブログ・せどり、その他、色々なものに挑戦していければと思います。
まだまだ、副業については、成果に結びついていないのが正直なところです。
しかし、着実に会社員としての収入(給与・賞与)を得つつ、余剰資金は投資に回すことで多くのリターンが生じています。
逆に今後、投資に関して芳しくない時期もあるのは避けられないので、そうした時は、給与・賞与や副業収入といった別の収入源でフォローできるような形に育てておきたいです。

収入源の複線化
つまり、リスク分散が大切ですね。
上記では簡単な説明にとどめていますが、投資に関する詳細記事は以下にまとめていますので、お時間ありましたらご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
本記事では、収入の複線化についてまとめました。
この収入源の調子が良くなくても、他の収入源があるからまぁ、大丈夫か。
そんな心の余裕が生まれるのが、収入の複線化の一番のメリットだと筆者は感じています。
そして、そうした会社員としてのお給料をもらう以外にも何か収入源が発生させられないか、そうした試行錯誤すること自体に価値があると感じています。

失敗は成功のもと、
引き続き色々なことに挑戦していきます。
頑張りましょう。
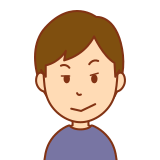
はい!!
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
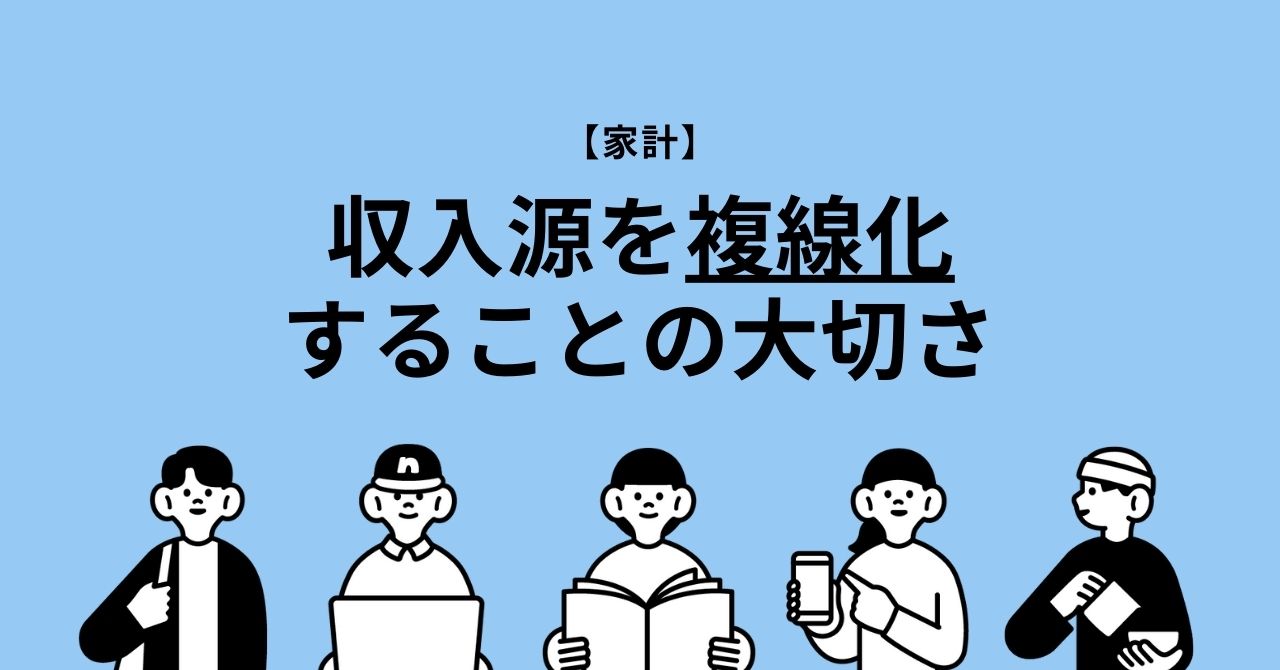
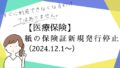
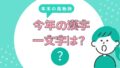
コメント