はじめに
最近の世間の動向としては、色々なものの機能・役割を集中する(一つに集約する)流れにあるように感じます。

機能を集中したほうが日々の生活では便利な反面、
何かあった時の被害が大きくなるリスクは高まります。
本記事では、集中と分散に関する所感をまとめます。
結論としては、どちらか一方が良いというわけではなく、メリット・デメリットを念頭に置きつつ、使い分けていく必要があると感じています。

”どちらか一方だけが良い悪い”
ということではないですね。
所感 ※”集中と分散”
本件に関する、所感は以下です。
- マイナンバーカード 編
- マイナ保険証 編
- マイナ免許証 編
- 財布の中身は、どこまでシンプルにできるか?

一つずつ見ていきます。
マイナンバーカード 編

マイナンバーカード自体に関する詳細は割愛しますが、個人番号(マイナンバー)に紐づける形で、色々な機能が集約されますね。
- 確定申告(e-Tax)
- スマホの契約時のネットでの本人確認
- コンビニでの住民票・戸籍謄本の発行
- 健康保険証として利用できる
- 昔は、ICカードリーダーが無いと読み取りできなかったが、
最近はスマホからの読み取りも可能 - 個人を一意に特定するマイナンバーが、カード上に明記されている。
→カードを紛失した際に、第三者に、顔写真とマイナンバーが紐づけて特定されてしまう。。 - マイナンバーカードに、署名用の電子証明書と利用者証明用の電子証明書を設定する必要がある。
→パスワード管理が重要。パスワード紛失時の対応が煩雑。
マイナンバーカードの詳細は、以下のマイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
また、マイナンバーカードのメリットがあります。
- カード1枚で、色々なことができる。
- 家に居ながら、色々なオンライン手続きが完結する。(e-Tax、スマホ契約等)

色々な情報が集約しているほうが、
日々の生活では便利ですし、
自宅に居ながら、色々な手続きが完結するのは便利ですね。
デジタル社会に生きていることを実感します。
一方で、以下のようなデメリットもあります。
- カード1枚で、色々なことができる。
- マイナンバーカードを紛失した際に、第三者にマイナンバーと顔写真その他諸々の情報が特定されてしまう。

カード1枚で色々なことができるのは、
メリットでもありますが、
デメリットにもなりえますね。
端的にいうと、以下のことが言えます。
- 平時 :日々の生活では、機能を集約したほうが便利。
- 非常時:カード紛失時等の非常時は、機能を集約していたことで被害が拡大する。
日々の日常の生活で利便性と、非常時に備えたリスク分散(安全性)。

バランスの難しい問題ですね。
このあたりの利便性と安全性の良い塩梅は、永遠の課題かもしれません。
世間的には、利便性を追求する方向に傾いている気がしますが、非常時の安全性についてもしっかりと考えていきましょう。
マイナ保険証 編
最近は、マイナ保険証も話題ですね。
マイナンバーカードに、紙の保険証の機能を集約するという流れですね。

紙の保険証を持ち歩かなく済み利便性は増します。
一方で、マイナカードを持ち歩く必要があり、
抵抗感も個人的には増します。
マイナ保険証に関する詳しい説明については、以下の厚生労働省のホームページ説明をご覧ください。
2024年12月2日で、紙の保険証の新規発行が停止されるため、マイナ保険証の準備に焦っているという方も多いのではないでしょうか。

我が家でも、
マイナ保険証の準備については、
喫緊の課題です。
筆者以外の家全員、マイナカードを
作成するところからのスタートです。。
マイナ保険証に関しては、世間での利用率や政府のマイナ保険証普及への強硬姿勢に疑問を呈する方も多いように見受けられます。
マイナ保険証に関して、よくある勘違いは以下ではないでしょうか。
- (勘違いその1)「2024年12月2日以降、紙の保険証は一切利用できなくなる。」
→12/2以降も、1年間の有効期限があり、引き続き医療機関で利用可能。
※ただし、内容変更や紛失時の新規発行はされない点、要注意。 - (勘違いその2)「マイナ保険証は義務である。」
→マイナンバーカード自体が、任意取得の位置づけ。
医療としては、マイナ保険証での受診を基本とする政府方針。 - (勘違いその3)「紙の保険証廃止後、マイナ保険証以外の手段はなくなる。」
→マイナ保険証以外にも、”資格確認書”が有効期限最長5年の範囲で利用可能。
マイナ保険証をお持ちでない方については、ご本人の申請によらず、
加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定(厚労省HPより)。 - (勘違いその4)「マイナ保険証を所持していても、資格確認書は交付される。」
→マイナ保険証を所持している場合、資格確認書は交付されない。
資格確認書を利用したい場合は、マイナ保険証の解除申請の申請が必要。
(マイナ保険証か資格確認書のどちらかを利用することに。)
個人的な見解ですが、政府としては、マイナ保険証の所持率を向上したいために、積極的には資格確認書の存在は周知していないように感じます。

厚生労働省のホームページ内には、
資格確認書の案内が、一応小さく明記されています。
また、資格確認書の有効期限(最長5年)が過ぎたあとに、マイナ保険証のみが唯一の手段となるのか等は、まだ案内がないかと思われます。
仮に、マイナ保険証のみとなった場合、任意であるはずのマイナカード取得が実質義務化されるといっても過言ではないかもしれません。
おそらくは、今後の議論として挙がってくるものと思われますが、そうした医療制度全体の動向にも注目していきます。

補足として、
医療のDXのためには、
マイナ保険証の存在は欠かせないものと感じます。
我が家における、マイナ保険証をめぐる導入は以下を考えています。
- 私&妻 →iPhoneに、マイナ保険証搭載ができるようになったら、
マイナ保険証を登録し、マイナカードは持ち歩かずにスマホで保険証も完結。
それまでは、資格確認書で粘る。。^^; - 子供達 →基本的には、資格確認書で粘る。
資格確認書の有効期限(最長5年間)到来後に、
マイナ保険証以外の大体手段があれば、そちらで対応。
のちのち、マイナカードの必要性が生じるタイミングで、
マイナカード作成&マイナ保険証登録。

・なるべく、マイナカードは持ち歩きたくない。
・子供達のマイナカード作成は現状必要性を感じない。
・将来的な、マイナカード機能のスマホ搭載に期待。
という思いがあります。
スマホにマイナ保険証を搭載するということが可能になる日が来たら、利便性はより高まる分、スマホ紛失時の影響もより高まるので、所在確認の徹底が必要になりそうです。
マイナ免許証 編

最近の話題として、マイナカードに運転免許証の機能を搭載できるというものがあります。
マイナカードと運転免許証の機能を集約する流れになります。


2025年3月導入ということで、
2024年9月現在、半年後ですね。
あっという間ですね。
概要としては、以下の点があります。
- 免許証のデータをマイナカードに一本化
- 住所変更がワンストップ
- 講習はオンラインで受講可能
- 一本化は任意
- 免許センターや一部警察署で申請可能
- 既存の免許証は廃止せず、マイナ免許証と両方所持可能
- 手数料的に、マイナ免許証のみが、一番お安く済む
マイナ免許証については、講習がオンラインで受講可能というメリットは魅力に感じます。
ただ、一本化は任意ということで、筆者としてはしばらく様子見だと考えています。
理由としては、以下です。
- 財布から運転免許証は所持しなくて済むが、代わりにマイナカードを持ち歩く必要が発生
→マイナカードを持ち歩きたくない。 - 一本化の対応のために、免許センター等に足を運ぶ必要がある
→一本化の対応負荷が高い。 - 免許の更新頻度は数年おき
→オンライン講習のメリットも数年おきしか教授できない - 運転免許証の色分け(グリーン・ブルー・ゴールド)が無くなる
→ゴールド免許保持者としての自覚を保持したい。安全運転につながる。
実際のマイナ免許証の運用が始まってから、また考えが変わるかもしれませんが、現時点は上記だと感じています。

マイナ免許証も、スマホへ搭載できる流れになるのかは気になります。
財布の中身は、どこまでシンプルにできるか?

マイナカードに色々な機能を集約し、保険証や運転免許証を持ち歩かなくて済むとなった場合、財布の中身はどこまでシンプルにできるでしょうか?
- 1万円札1枚(お守り)
- クレジットカード2枚(プライベート用+副業用)
- 銀行キャッシュカード1枚
- 運転免許証1枚
- 保険証1枚
↓ - 合計カード5枚
上記が、マイナカードに色々と機能集約後は、、
- 1万円札1枚(お守り)
- クレジットカード2枚(プライベート用+副業用)
- 銀行キャッシュカード1枚
運転免許証1枚保険証1枚- マイナンバーカード1枚(マイナ保険証・マイナ免許証)
↓ - 合計カード4枚
上記のように、カード1枚分の節約が可能となります。
マイナンバーカード機能をスマホに搭載できるようになった場合、マイナンバーカードを持ち歩く必要がなくなるので、上記合計からさらに1枚引いて3枚となります。
- カード1枚分を削って、保険証機能と運転免許証機能を集約するのか、
- さらに、カード1枚分削って、スマホへさらに機能を集約するのか、
どこまで機能を集約するか(=機能の集中と分散の度合い)は、難しい問題です。
あえてカードを別々にして、機能を分散させておくのも一手かもしれません。

そもそも財布自体を紛失した場合は、
どちらにしても、影響は大きいですが。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
本記事では、マイナンバーカード・マイナ保険証・マイナ免許証に関する昨今の動向からの所感をまとめました。
本記事では、マイナカード関連の話に特化したないようとなりましたが、集中と分散の話は他にも色々なことに当てはまる論点です。
- ITシステム
→クラウドシステムで一元集約 or 分散系のシステム - 投資
→個別株投資 or 分散投資(長期投資・投資信託・ETF) - 企業運営
→国内集中経営 or グローバル経営 - コミュニティ
→家族、会社、第三のコミュニティ

色々な論点に通じる話ですね。
このあたりはまた別の機会で
所感をまとめたいと思います。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
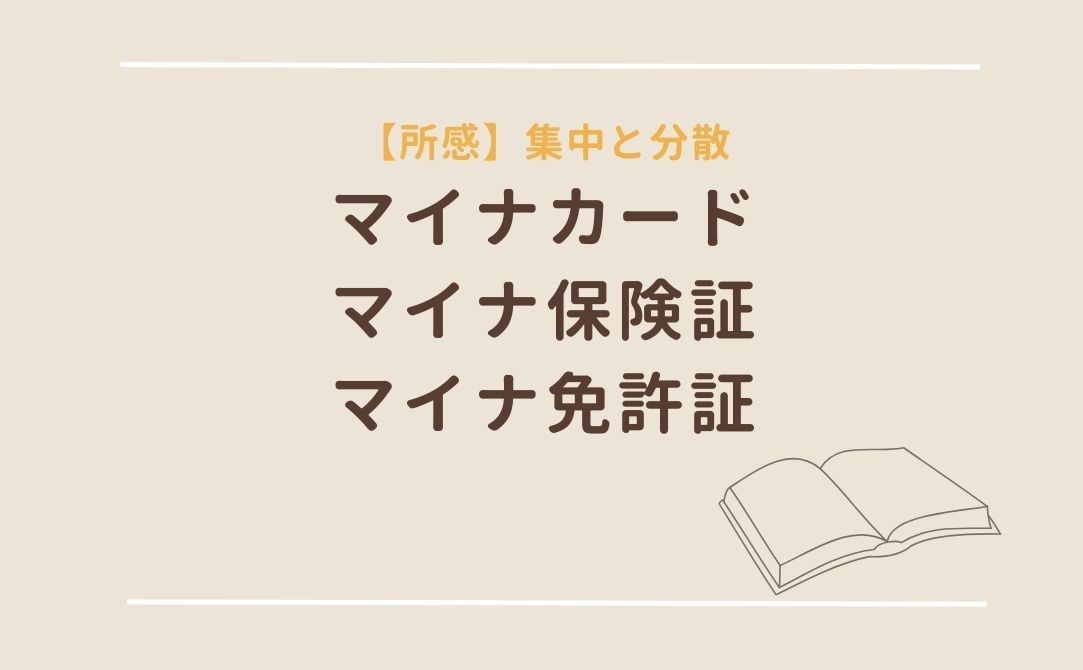
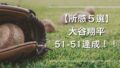
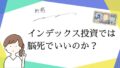
コメント