はじめに
2024年度がスタートし、まだ数日ですが、環境の変化に戸惑う場面も多々あります。
色々と理由はあるかと思いますが、”先の予測できない恐怖”というところが一定程度あるように感じます。
本記事では、そうした所感についてまとめます。
考えるきっかけとなった出来事
考えるきっかけとなった出来事として以下の出来事がありました。
- 朝の保育園登園時
- 玄関前で泣きじゃくり登園に抗っている子(2才程度)
我が子(年少)は、昨年からその保育園に通い始めたこともあり、特にぐずることもなく毎朝保育園への登園も嫌がりません。
しかし、保育園へ行き始めの子からすると、いきなり未知の場所に家族もいない中一人取り残される恐怖は尋常ではないと感じます。

筆者も、幼いころの記憶として、
保育園初登園時の不安感は少し記憶にあります。。
所感(先が予測できない恐怖との戦い)

その出来事をうけての、所感は以下です。
- 予測できない恐怖との戦い
- 知る事・学ぶことの意義
- 習慣化のメリット(新生活の中での”いつもの作業”の安心感)

一つずつ見ていきます。
予測できない恐怖との戦い
上記の保育園登園時の例でいうと、
大人からすると自身の経験値から保育園での過ごし方や様子がある程度予測がつきます。
しかし、子供からすると、未知の体験・初めての体験のため、保育園がどういったところか・今後どのような生活となるのか、という恐怖が先立つのではないでしょうか。
先を予測できない恐怖
この部分の恐怖はすごくあるように感じます。
保育園の例に限らず、”先を予測できない恐怖”は、人生においてたくさんあるのではないでしょうか。
- これからどの小学校・中学校・高校にいくのか
- どの大学にいくのか
- どの会社に就職するのか
- 家
- 車
- パートナー・子供
- 老後はどのような生活を送っているのか
- ライフプラン
- お金
例を挙げだすときりがないですが、
若かりし頃の漠然とした不安感を感じる一つに、こうした将来の予測のつかなさが一因だと感じます。

筆者自身も、
思春期は先の見えない将来に
思い悩んだ時期もありました。
知る事・学ぶことの意義
そうした恐怖を少しでも緩和するために、社会の仕組みを知る事や学ぶ意義があると感じます。
当然、すべてを予測することは不可能ですが、
社会の仕組みやライフプランの年齢ごとの大体の相場観を知っておくだけで、
自分自身の生活での予測がある程度できるように感じます。
筆者としては、以下のような対応を日々しています。
- 社会の仕組みを知る
…日経新聞購読、FP3級のテキストで社会の仕組みを勉強 - 学ぶ
…youtube勉強動画、SNS、電子書籍等で有益な情報をインプット - ライフプランニング表の作成
…各年齢・家族構成に応じた、必要イベント・収支の予測の見通しを立てる
このあたりの家計・ライフプランニング表周りの知識は、FP3級のテキストで一通り勉強できるため、FP資格自体を受験しないとしても一通り、テキストを読むと理解が深まると感じます。
習慣化のメリット(新生活の中での”いつもの作業”の安心感)
新生活で、新しい作業・なれない作業に違和感を感じる日が続きますが、
そうした新生活の不安への対処法として、”習慣化”が有効だと感じます。
- 朝一での日経新聞購読
- X(旧Twitter)での情報発信
- ブログ執筆
- 定期的な運動(筋トレ・ランニング)
先が読めない日常の中で、いつも行っている作業をこなした時の安心感
そうしたものが感じられるメリットが、諸々の作業の習慣化にあると感じます。
どのような作業を習慣化するかは、人それぞれなので、
各自の習慣化できるものを継続するのがよいのではないでしょうか。
まとめ

いかがでしたでしょうか。
本記事では、新生活で先の読めない恐怖への所感についてまとめ、どのような対策がとれるかについて所感をまとめました。
まだまだ、新生活スタートしたばかりで、慣れない生活の日々が続きますが、頑張りましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。

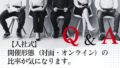

コメント